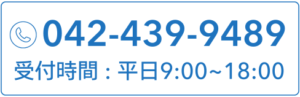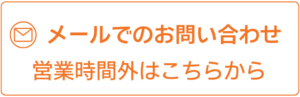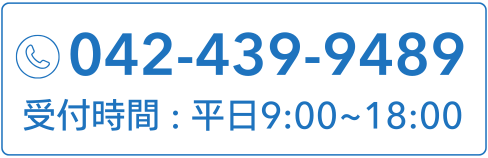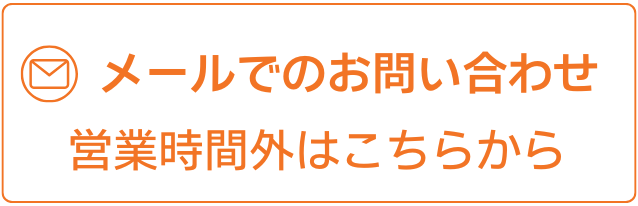相続税の基礎知識を知ることで、相続手続きを進める際の理解が深まります。相続税は、被相続人が遺した財産に対して課される税金で、一定の基礎控除額を超える場合に申告・納税が必要となります。
相続税の概要
相続税は、被相続人から受け継いだ財産に対して課税される税金です。財産には、現金や不動産、株式などの金融資産、さらに美術品や車などの動産も含まれます。また、生命保険金や死亡退職金も相続財産の一部として扱われることがあります。
相続税の基礎控除
相続税の計算において重要なポイントは、基礎控除額です。
基礎控除額とは、相続財産の総額から引かれる金額で、この基礎控除額以下の財産には相続税が課されません。
基礎控除額は次の計算式で算出されます。
- 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数
たとえば、法定相続人が3人(配偶者と子2人)の場合、基礎控除額は次のようになります。
- 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
上記のケースで被相続人の財産が4,800万円以下の場合は、相続税の申告対象にはなりませんので、申告手続きは不要となります。
あくまでも基礎控除額を超える相続財産がある場合のみ、相続税の申告・納付が必要となります。
課税対象の財産
相続税の対象となる財産には、以下のようなものが含まれます。
- 不動産(土地、建物など)
- 金融資産(預金、株式、債券、貸付金など)
- 動産(車、貴金属、骨董品など)
- その他(特許権、著作権など)
- 生命保険金(一部非課税枠あり)
- 死亡退職金(一部非課税枠あり)
ただし、負債(借金や住宅ローンや葬儀費用など)は相続財産から差し引くことができます。
相続税の計算方法
相続税の計算は次のステップに従って行われます。
(1) 相続財産の総額を算出
被相続人が所有していた財産の総額を計算します。
負債や葬儀費用を差し引いた後の純資産が相続財産の金額となります。
(2) 基礎控除額を差し引く
相続財産の総額から基礎控除額を差し引き、相続税の課税対象となる金額を計算します。
(3) 相続税の総額を計算
相続税の課税対象となる金額に各相続人の法定相続分の割合を掛け、各相続人の法定相続分に応じた金額を求めます。
その求めた各金額に対して、それぞれ相続税の税率を適用して相続税を計算し、それぞれの相続税を合計します。その合計した金額が相続税の総額と呼ばれ、被相続人の財産全体に対して課税される相続税の全体額となります。
| 課税遺産額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | なし |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
(4) 各相続人の負担額を決定
上記で計算された相続税の総額を実際に財産を取得した割合で各相続人が負担することとなります。
なお、相続人の続柄や状況に応じて、配偶者控除や未成年者控除などの税額控除が適用されることがあります。
相続税の控除・特例
相続税には、特定の条件下で税負担を軽減するための控除や特例が用意されています。主な控除や特例は次の通りです。
(1) 配偶者控除
配偶者が相続する財産については、法定相続分又は1億6,000万円のいずれか高い金額までの財産については相続税がかかりません。これにより、配偶者が相続する際は相続税の負担が大幅に軽減されます。
(2) 小規模宅地等の特例
被相続人が居住していた土地や、事業用の土地については、最大80%まで評価額が減額される特例があります。この特例を適用することで、土地の評価額が大幅に下がり、相続税の負担が軽減されます。
(3) 未成年者控除
相続人が未成年である場合、満18歳に達するまでの年数に応じて控除が適用されます。控除額は、1年につき10万円です。
(4) 障害者控除
相続人が障害者である場合、満85歳に達するまでの年数に応じて、1年につき10万円(特別障害者は1年につき20万円)の控除が適用されます。
(5) 相次相続控除
10年以内に2回相続が発生した場合、同じ財産に対して短期間の間に2 回相続税が課税されることとなる為、一次相続で納付した相続税の一部を二次相続時の相続税から控除することができます。
相続税の申告と納付
相続税の申告と納付は、相続開始から10ヶ月以内に行わなければなりません。申告が必要な場合、税務署に相続税の申告書を提出し、納税手続きを行います。現金での一括納付が難しい場合、一定の要件を満たすことにより延納や物納の制度を利用することも可能となます。
- 延納
相続税を分割で納付する方法 - 物納
現金での納付が困難な場合に、不動産や株式などの財産で納税する方法
相続税の申告が不要な場合
相続財産(負債や葬式費用を控除した後の金額)が基礎控除額を超えない場合、相続税の申告手続きは不要となります。ただし、小規模宅地の特例を適用して基礎控除額以下となった場合は申告が必要となりますので、ご注意ください。
相続税の制度は複雑ですが、相続税の専門家である税理士に相談することで適切な対応が可能となります。特に、多額の財産がある場合、不動産が多い場合、相続人が多数いる場合等には、早めに準備を進めることが大切です。