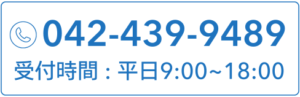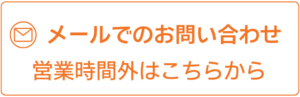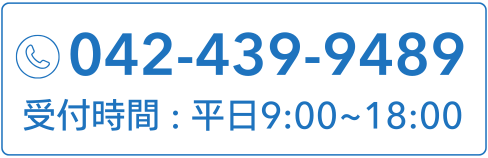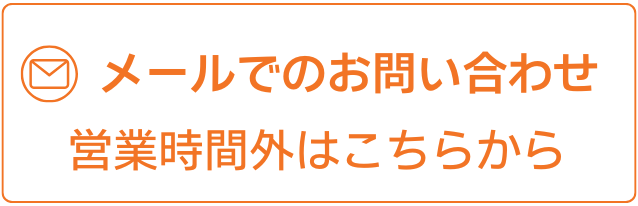相続は被相続人(亡くなった方)が亡くなった時点で開始され、この時点から遺産分割協議や相続税申告の手続きの準備を徐々に進めていくことになります。
ポイント
- 死亡診断書や戸籍謄本を取得し、被相続人の死亡を公式に証明する。
- 相続の各種手続きに必要な書類を収集する。
被相続人が遺言書を作成していた場合、遺言書が相続手続きの基本となります。遺言書の確認は慎重に行う必要があり、次の点に注意します。
ポイント
- 公正証書遺言がある場合は、公証役場に保管されており、その内容に従います。
- 自筆証書遺言がある場合は、家庭裁判所で検認手続きが必要です。この検認は、遺言書が無効か有効かを判断するものではなく、あくまで遺言書が改ざんされていないかを確認するものです。
- 遺言書に基づいて財産の分割が進められますが、法定相続人の遺留分を侵害する場合には、遺留分侵害額請求ができる場合があります。
被相続人の法定相続人が誰であるかを確認するために、被相続人の出生から相続発生までの戸籍を詳しく調べる必要があります。
ポイント
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、法定相続人が誰かを確定する。
- 配偶者、子供(嫡出子・非嫡出子)、養子、直系尊属(親)、兄弟姉妹などが相続人となる可能性があります。
- 相続人の中には、相続人に該当しないという主張(相続欠格・相続廃除)をする場合もあり、その際は遺産分割協議を円滑に進めるために法律の専門家である弁護士に早めに相談することが推奨されます。
遺産の種類や金額を確認し、負債がないかどうかも同時に調査します。
ポイント
- 不動産
不動産登記簿を確認し、土地や建物の所有者や評価額を把握。 - 預貯金
銀行口座や証券口座の残高証明書を取得。 - 株式や有価証券
証券会社や保有している株式の内容を確認。 - 負債
借金、ローン、保証債務などの負債がある場合、その内容を確認。 - 動産
車や貴金属、美術品などの動産も遺産に含まれる。
この時点で、すべての財産と負債を把握し、相続人間で話し合いを進めるための資料を揃えます。
相続人は、被相続人の負債が多い場合やその他の事情で、相続を放棄することができます。これには以下の選択肢があります。
ポイント
- 相続放棄
期限:相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きが必要。
手続き:家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、審理を経て認められる。これにより、相続放棄をした相続人は最初から相続人ではなかったとみなされる。 - 限定承認
被相続人の財産を相続しつつ、財産の金額を超えない範囲でのみ負債の返済義務を負う方法。
期限:こちらも相続放棄と同様に3ヶ月以内に家庭裁判所での手続きが必要。
相続人全員が集まり、遺産をどのように分けるか話し合います。法的には、以下のポイントに従って協議を進めます。
ポイント
- 法定相続分に従って分割する場合や、相続人全員の合意に基づいて法定相続分以外の割合に分割することも可能。
- 不動産の取得者や、現金の配分、株式などの資産について、具体的な取り決めを行う。
- 遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印して正式な合意を得る。
協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができる。
相続税の課税対象となる場合、次のような手順を踏みます。
ポイント
- 申告期限
相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告と納付を行う。 - 税務署での手続き
相続税の申告書を被相続人の最後の住所地を管轄する所轄税務署に提出する。
相続税の納税額は、遺産の総額と法定相続分、基礎控除額に基づいて計算される。 - 基礎控除
3,000万円+600万円×法定相続人の人数が基礎控除額となり、この額を超える財産が課税対象となる。
遺産分割協議や相続税の申告手続きが完了した後、遺産に含まれる不動産や預貯金口座の名義を変更します。手続きの手順は次の通りです。
ポイント
- 不動産の名義変更
法務局で登記申請を行い、被相続人から相続人への所有権移転登記を行う。
必要書類には、遺産分割協議書、相続人の戸籍謄本、固定資産税評価証明書などがある。 - 銀行口座の解約や名義変更
金融機関に対して、相続人全員の合意書や遺産分割協議書を提出し、口座の解約や名義変更を行う。
全ての財産及び債務の遺産分割と名義変更等の手続きが終わると、各相続人が正式に相続財産を承継したことになります。なお、相続手続き後も引き続き保管が必要な書類も多いので、重要書類はしっかりと保管しましょう。